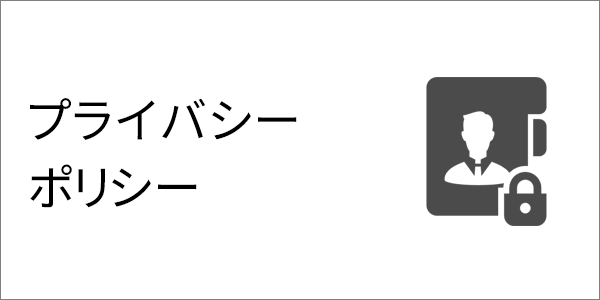宣伝されていた「夢の技術」というイメージと、実際に使ってみた時の体験にギャップがあると感じている方は少なくありません。なぜ速くないのか?いくつかの理由が考えられます。
理論値と実測値のギャップ

5Gは理論上、最大で10Gbps(ギガビット/秒)もの速度が出ると言われています。これは4Gの最大1Gbpsと比較して桁違いに速いです。でも、全然速く感じないですよね?
これはあくまで理想的な条件下での理論値であり、実際に利用する環境では様々な要因で速度が低下してしまうからです。
5Gの種類と周波数帯
5Gには大きく分けて以下の周波数帯があります。
Sub-6GHz帯(低・中周波数帯):比較的広範囲をカバーしますが、速度は4GLTEと大きく変わらないか、わずかに速い程度です。多くの場所で接続されるのはこの帯域であることが多いです。
ミリ波(mmWave、高周波数帯):非常に高速ですが、電波の直進性が強く、障害物に弱く、届く範囲も狭いという特性があります。そのため、基地局の設置密度を高くする必要があり、限られたエリアでの利用が中心です。
もし接続している5GがSub-6GHz帯であれば、体感速度が4Gとあまり変わらないと感じるのも無理はありません。
ネットワークの整備状況
5Gのネットワークはまだ発展途上にあります。特にミリ波の基地局は、建物の壁や樹木などによって電波が遮られやすいため、より多くの基地局を設置する必要があります。
現状では、まだ十分にインフラが整備されていない地域も多く、結果として安定した高速通信ができないことがあります。
日本における5Gの状況としては、Opensignalの2022年の調査では、韓国や台湾といった他の東アジア諸国と比較して、日本の5Gは電波強度が低い傾向にあり、それが速度低下に繋がっている可能性が指摘されています。
また、利用できる時間帯も限られているという報告もありました。
その他の要因
電波状況と障害物:基地局からの距離、建物や地形、さらには屋内か屋外かによっても電波の届きやすさが変わります。ミリ波は特にこれらの影響を受けやすいです。
ネットワークの混雑:ピーク時間帯など、多くのユーザーが同時に接続している場合は、ネットワークが混雑し、速度が低下することがあります。
使用している端末の性能:5Gに対応していても、端末の性能(アンテナやモデムの性能)によっては、最大限の速度が出ない場合があります。おま環ですね。
契約プランや通信制限:キャリアによっては、一定のデータ量を超えると通信速度が制限される場合があります。
まとめ
5Gは「速い」という宣伝が多い一方で、実際にその恩恵を十分に受けるためには、対応する周波数帯、ネットワークの整備状況、利用環境、端末の性能など、様々な要素が揃う必要があります。
現状では、特に日本においては、理論上の最大速度を常に体験できるわけではなく、まだまだ発展途上の技術であると言えるでしょう。
5Gを取り扱う企業の業績

企業の種類や事業内容によって異なる状況にあります。大まかに分けると、以下のカテゴリーで捉えることができます。
通信事業者(キャリア):NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルなど
課題:5Gへの多額な設備投資が必要な一方で、消費者向けの5Gサービス単体での収益化が難しいという課題に直面しています。従来のデータ通信量に基づく課金モデルだけでは、投資を回収しきれないという声が多く聞かれます。
取り組み:BtoB領域の強化:企業向けにローカル5GやMEC(マルチアクセスエッジコンピューティング)を活用したソリューションを提供し、新たな収益源を模索しています。スマート工場、遠隔医療、自動運転など、多岐にわたる分野での実証実験や導入が進められています。
コスト効率化:基地局の共同利用やOpenRANの導入などにより、設備投資コストの抑制を図っています。
DX推進:自社のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、業務効率化や新たなサービスの創出を目指しています。
業績動向:各社とも法人事業やスマートライフ事業(金融、決済、コンテンツなど)が好調に推移し、全体としては増益を達成している企業が多いですが、これは5G単体の収益というよりも、多角的な事業展開によるものです。通信事業者の5Gへの投資は今後も継続される見込みですが、いかに「マネタイズ」していくかが大きな課題となっています。
5G関連機器・部品メーカー:エリクソン、ノキア、ファーウェイ、サムスン、NEC、富士通、村田製作所、TDKなど
状況:5Gインフラの整備が進むにつれて、基地局や通信機器、関連部品の需要は堅調に推移しています。特に、ミリ波対応の高性能な部品や、データセンター向けの光回線機器などを手掛ける企業は、AI関連需要の増加も追い風となり、好調な業績を維持しているところが多いようです。
主要企業と動向:
グローバル大手(エリクソン、ノキア、ファーウェイ、サムスンなど):世界の5Gインフラ市場を牽引しており、各国の投資状況に大きく左右されます。一部の国では地政学的リスクによる影響も受けています。
日本企業(NEC、富士通など):国内キャリアの5G基地局ベンダーとして実績を積んでおり、OpenRANなど国際的な取り組みにも参加することで、海外市場への展開も図っています。
電子部品メーカー(村田製作所、TDKなど):5G端末や基地局に不可欠な高性能部品(積層セラミックコンデンサ、フィルターなど)を提供しており、安定した需要があります。
市場予測:5Gインフラ市場は2025年に145.6億米ドルに達し、2030年には1,016.8億米ドルに成長すると予測されており、関連デバイス・材料市場も引き続き拡大が見込まれます。
5G関連ソリューション・サービスプロバイダー:エクシオグループ、NECネッツエスアイ、BIPROGY、フリービットなど
動向:5Gネットワークの構築支援、IoTソリューション、エッジコンピューティング、プライベート5Gの導入支援など、5Gを活用した新たなサービスを提供する企業です。特に企業向けのDX(デジタルトランスフォーメーション)支援の需要が高まっており、堅調な業績を上げている企業が多いです。
特徴:5Gの「速さ」や「低遅延」といった特性を活かした具体的なユースケースを提案し、企業や自治体の課題解決に貢献することで収益を上げています。
総括
5Gを取り巻く企業全体としては、投資が先行する通信事業者において収益化の課題は残るものの、BtoB領域や新たなサービス開発へのシフト、コスト効率化の取り組みが進んでいます。
一方、機器・部品メーカーやソリューションプロバイダーは、5Gインフラの整備やDX需要の拡大を背景に、堅調な業績を維持している企業が多いと言えます。
AI(人工知能)との融合も注目されており、「AIforRAN」(AIによる無線アクセスネットワークの効率化)や「AIandRAN」(AIとRANの統合による新たな収益機会創出)といった領域での研究開発も進んでおり、今後の成長ドライバーとなる可能性があります。
5Gはまだ発展途上の技術であり、その真価が発揮されるのはこれからとも言われています。まだまだこれから、というところですね。
各企業には、技術革新と市場ニーズの変化に対応しながら、新たな収益モデルを確立していくことが求められています。