日本の半導体産業は、かつて世界を牽引した時代から一転し、半導体チップの製造分野においてはアメリカや台湾の後塵を拝しているという認識が広く浸透しています。このような状況下で、東京エレクトロン(以下、TEL)が半導体製造装置の分野で世界的なリーダーシップを確立し、業界を牽引していることは、一見すると矛盾しているように映るかもしれません。今回は、この問いに対し、日本の半導体産業の多層的な構造を解き明かし、その中でTELが突出した存在となり得た戦略的要因を詳細に分析していきます。
はじめに:東京エレクトロンの特異な存在感
![]()
TELは、半導体チップそのものを生産する企業ではありませんが、その製造に不可欠な「半導体製造装置」の開発、製造、販売において世界トップクラスのシェアを誇る日本の大手企業です。
世界の半導体製造装置市場は2023年に約900億ドル規模と推定され、今後もさらなる成長が見込まれる巨大市場であり、TELはこの市場において売上高ランキングで世界第3位に位置しています。
このTELの存在は、半導体産業が単に「チップ製造」だけでなく、それを支える「製造装置」や「材料」といった複数のレイヤーで構成されていることを明確に示しています。
ユーザーが抱く「日本の半導体産業の遅れ」という認識は、主に半導体チップの設計や製造(ファブレス・ファウンドリ)分野に焦点を当てたものであり、半導体製造装置や材料といった川上・川中分野における日本の揺るぎない強みを見過ごしている可能性があります。
TELの卓越した地位は、日本の半導体産業が特定の分野で依然として極めて高い競争力を持っていることを示しており、全体的な「遅れ」という見方をより多角的に捉え直す必要性を浮き彫りにしています。
日本の半導体産業の多層構造:チップ製造と装置・材料の乖離
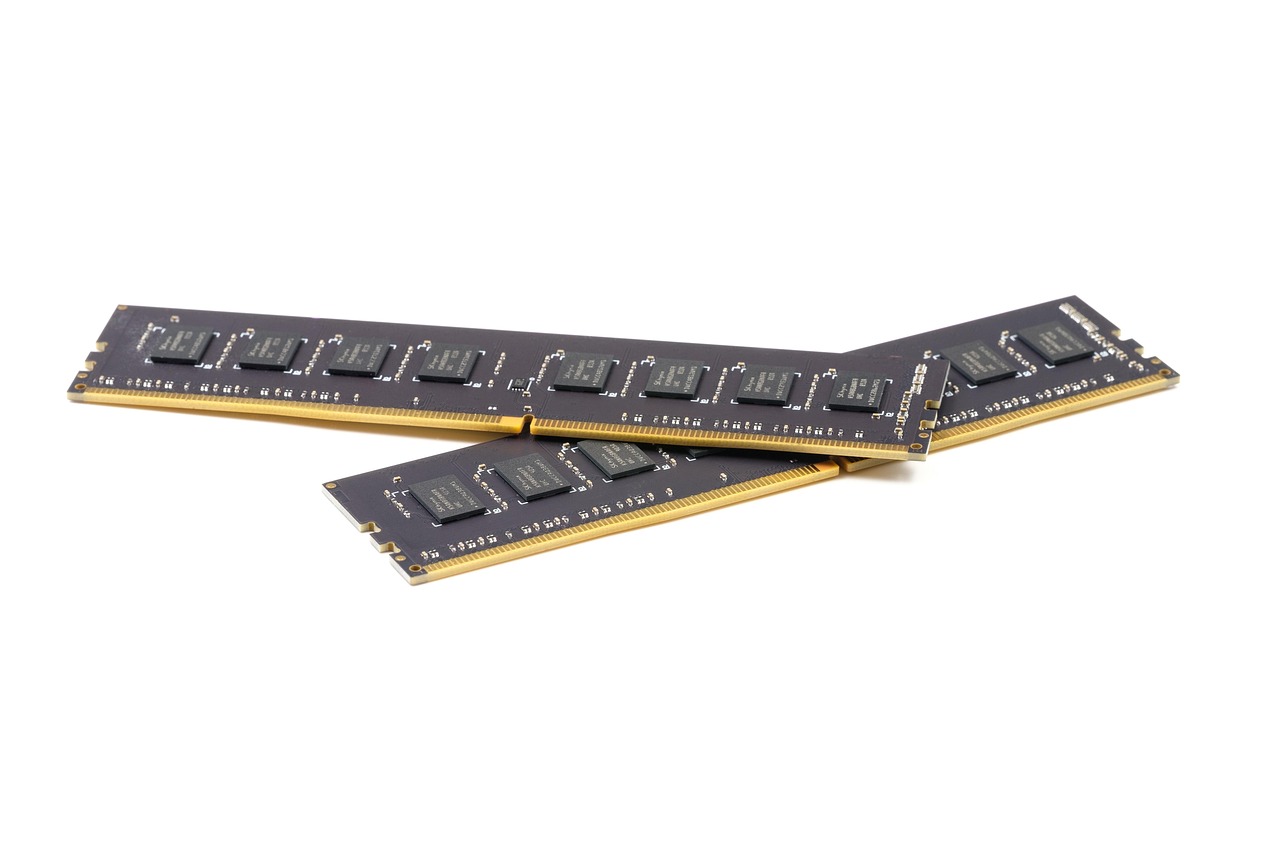
日本の半導体産業は、1980年代にはDRAMなどのメモリ分野で世界市場を席巻していましたが、その後急速に競争力を失っていきました。この衰退には複数の要因が複合的に絡んでいます。
まず、日米半導体協定が挙げられます。1980年代の日本の半導体産業の急速な台頭は、アメリカとの間で激しい貿易摩擦を引き起こしました。
1986年に締結された「日米半導体協定」では、日本市場における外国製半導体のシェアを当時の約10%から20%に引き上げるという不平等な購買義務が日本に課され、これにより日本の半導体開発の勢いが著しく削がれる一因となりました。
次に、主要マーケットの移り変わりと戦略思考の欠如が指摘されます。半導体市場は、それまでの通信機器や大型コンピュータ向けの「高品質・長寿命」を重視するDRAM中心の時代から、パソコンの普及に伴い「安価で短寿命」な汎用ロジックやメモリが求められる時代へと変化しました。
当時の日本の大手半導体メーカーの多くは、半導体部門が総合電機メーカーの一部門に過ぎず、経営トップ層が半導体ビジネスの特性に深く精通していないことが珍しくありませんでした。このため、不況時に先行投資を行い、好景気になってから売上を伸ばすという、半導体産業に不可欠な戦略的投資判断が困難であったとされます。
さらに、日本の半導体メーカーが設計から製造までを一貫して行う垂直統合型(IDM)ビジネスモデルに固執したことも、競争力低下の決定的な要因となりました。
海外では、設計に特化したファブレス企業や、製造に特化したファウンドリ企業が登場し、水平分業型が主流となっていきました。
日本の企業はこの水平分業化の流れに乗り遅れ、得意分野の確立が遅れた結果、国際競争力を失っていきました。このビジネスモデルの選択と、市場環境の変化への適応の遅れが、日本の半導体チップ製造業の競争力低下を招いた主要因の一つと考えられます。
加えて、業界再編への反応が鈍く、デファクトスタンダードとなる製品を生み出すための大規模な投資が不足したことも、日本の半導体産業の凋落を加速させました。
しかし、半導体産業全体を見渡すと、日本は半導体チップ製造とは対照的に、半導体製造装置や半導体材料といった分野で依然として世界的な強みを保持しています。特に、半導体製造に不可欠な「材料」分野では、日本企業が圧倒的な世界シェアを誇っています。
以下の表は、主要な半導体材料における日本の優位性を示しています。
表1:主要半導体材料の世界市場シェアにおける日本の優位性
| 項目 | 日本企業の市場シェア/特記事項 | 主要企業(日本) |
| 半導体材料全体 | 全体の48%を占める | – |
| シリコンウェーハ | 信越化学工業とSUMCOの2社で市場の半分以上を確保 | 信越化学工業、SUMCO |
| フォトレジスト | 日本企業5社で市場シェア92%を寡占 | JSR、東京応化工業、信越化学工業、住友化学、富士フイルム |
| マスクブランクス | HOYAが世界シェア70%。EUV向けはAGCが強み | HOYA、AGC |
| 高純度フッ酸 | 日本企業3社で市場シェア80-90% (2019年) | ステラケミファ、ダイキン工業、森田化学工業 |
| CMPスラリー | 日本企業が上位にランクインし、強みを持つ | レゾナック、フジミ、富士フイルム |
| スパッタターゲット | JX金属と東ソーの2社で市場シェアの半数以上を占める | JX金属、東ソー |
| 半導体後工程主要材料 | 日本企業が50%以上のシェア | 住友ベークライトなど |
| ハイエンド向けパッケージ基板 | イビデンと新光電気工業の2社で70-80%のシェア | イビデン、新光電気工業 |
| パワー半導体(チップ) | 三菱電機、富士電機、東芝などが世界シェア上位にランクイン | 三菱電機、富士電機、東芝、ルネサスエレクトロニクス、ローム |
この表が示すように、日本の半導体産業の強みは、半導体チップの製造そのものよりも、その製造を可能にする「材料」と「製造装置」という、いわば「縁の下の力持ち」の分野に集約されています。
TELの突出した地位は、この日本のサプライチェーンにおける特定の強みを体現するものです。
東京エレクトロンの卓越性:成功の戦略的要因
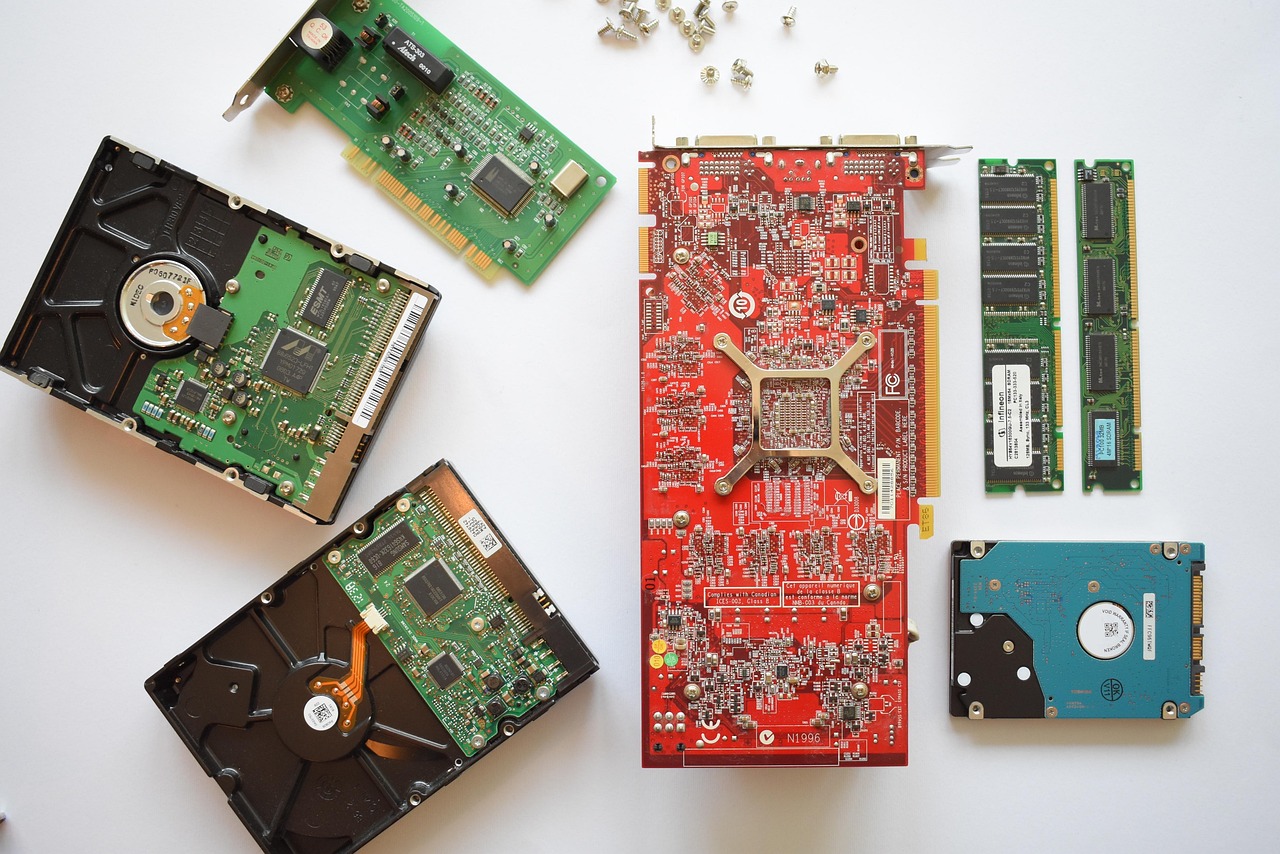
TELが半導体製造装置市場で世界をリードする存在となり得た背景には、多岐にわたる戦略的要因が存在します。
創業と歴史的転換点:輸入商社から製造メーカーへ
TELは1963年に、半導体製造装置を扱う技術専門商社としてその事業を開始しました。創業当初は、アメリカ製の先進的な半導体製造装置を日本市場に紹介する役割を担い、当時の日本の半導体産業の成長を支える重要な位置を占めていました。
しかし、1980年代に激化した日米半導体摩擦という外部環境の変化は、TELの経営戦略に大きな転換を迫ることになります。この状況下で、TELは単なる輸入販売にとどまらず、自社での製造(内製化)に踏み切るという大胆な決断を下しました。
これは、海外依存のリスクを低減し、技術の内製化によって競争力を高めるという戦略的な狙いがあったためです。
この内製化への決断と、合弁会社の株式取得(テルメック、テル・ラム、テル・サームコなど)を通じて製品ラインナップを拡大したことが、1989年には世界No.1の半導体製造装置メーカーとなる礎を築きました。
TELの成功は、市場の変化を的確に読み解く洞察力と、外部環境の変化に柔軟に対応し、自社のビジネスモデルを大胆に転換する戦略的実行力の賜物であると言えます。
技術革新と研究開発への飽くなき投資
TELの成功の核となるのは、その卓越した技術力と、それを持続させるための積極的な研究開発投資です。TELは、半導体の微細加工に不可欠な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という連続した4つのキープロセス全てに製品を持つ世界で唯一のメーカーです。
特に、半導体の進化に不可欠なEUV(極端紫外線)露光用の塗布現像装置においては、世界シェア100%を誇る「オンリーワン」の製品を有しています。
また、各セグメントにおいて市場シェア1位もしくは2位を獲得しており、その製品群の強さが際立っています。
このような技術的優位性は、継続的な研究開発と技術革新によって維持されています。TELは半導体製造装置業界においてグローバルNo.1の特許保有件数を誇り、その技術力の高さを示しています。
さらに、将来の成長を見据え、2025年3月期からの5年間で研究開発に1.5兆円以上の投資を計画しており、これは業界トップクラスの地位を維持するための「攻めの戦略」と位置付けられています。
自社開発に加え、顧客との共同開発や世界屈指のコンソーシアムとの協業を推進することで、革新的かつ多様な技術を創出しています。
半導体製造装置市場の寡占化は、莫大な研究開発投資が継続的に必要とされるため、新規参入が極めて困難であるという特性に起因します。
TELの積極的な研究開発投資戦略は、この市場特性を最大限に活用し、技術的優位性を維持・強化することで、競合他社の追随を許さない参入障壁を築き、強固な地位を盤石にしています。
顧客密着型開発と絶対的信頼関係
半導体製造装置は、単に製品を販売するだけでなく、顧客である半導体メーカーの製造プロセスに深く入り込み、その生産性や歩留まりに直接影響を与える特性を持っています。
TELは、世界最大の装置出荷実績(累計約92,000台)を通じて培った顧客との「絶対的信頼関係」のもと、技術サービスとマーケティングを展開しています。
これは、単に製品を提供するに留まらず、顧客が生産するデバイスの歩留まり向上や装置稼働率の最大化に貢献することで、顧客の課題解決を支援するものです。
この顧客密着型アプローチは、アフターマーケットにおける収益確保にも繋がっています。
パーツ販売やアップグレード改造、稼働率向上への取り組み、さらには遠隔保守サービスやAIを活用した予知保全など、高効率かつ高付加価値サービスの構築にも注力しており、これらの高度なフィールドソリューションの提供を通じて、安定的な収益源を確保しています。
半導体製造装置は高価で複雑であり、一度導入されると、その後のメンテナンスやアップグレード、プロセス最適化のために、同じメーカーからの継続的なサポートが不可欠となります。
これにより、顧客は特定の装置メーカーに依存する「ロックイン効果」が生じ、新規メーカーへの切り替えは極めて高コストでリスクが高くなります。
TELの顧客密着型開発とアフターサービス重視の戦略は、顧客との長期的なパートナーシップを構築し、単なるサプライヤーを超えた「不可欠な存在」としての地位を確立することで、この市場特性を最大限に活かし、競争優位性を不動のものにしています。
製品ラインナップの強みとニッチ市場での専門性
半導体製造プロセスは極めて複雑で多段階にわたるため、各工程で専門的な装置が必要となります。TELは、半導体製造の連続した4つのキープロセス(成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄)全てに製品を持ち、かつ各セグメントで市場シェア1位または2位を獲得している世界で唯一のメーカーです。
この包括的な製品ラインナップは、顧客である半導体メーカーにとって大きなメリットをもたらします。複数の主要工程の装置を一社から調達できることは、プロセス全体の整合性の確保、技術サポートの一元化、サプライチェーン管理の簡素化に貢献します。
他の競合他社が特定の工程に特化している中で(例えば、ASMLは露光装置、Lam Researchはエッチング装置に強みを持つ)、TELは包括的なソリューションを提供できるため、顧客との関係性をより深く、広範に構築することが可能です。
この「唯一性」は、単なる製品の幅広さ以上の戦略的価値を持ち、顧客の生産ライン全体にわたる「裏方」としての不可欠な存在感を強固にしています。
TELは、高付加価値の次世代装置の継続的な創出にも注力しており、将来の半導体技術革新を支える上で中心的な役割を担い続けることを目指しています。
半導体製造装置市場の特性と競争環境
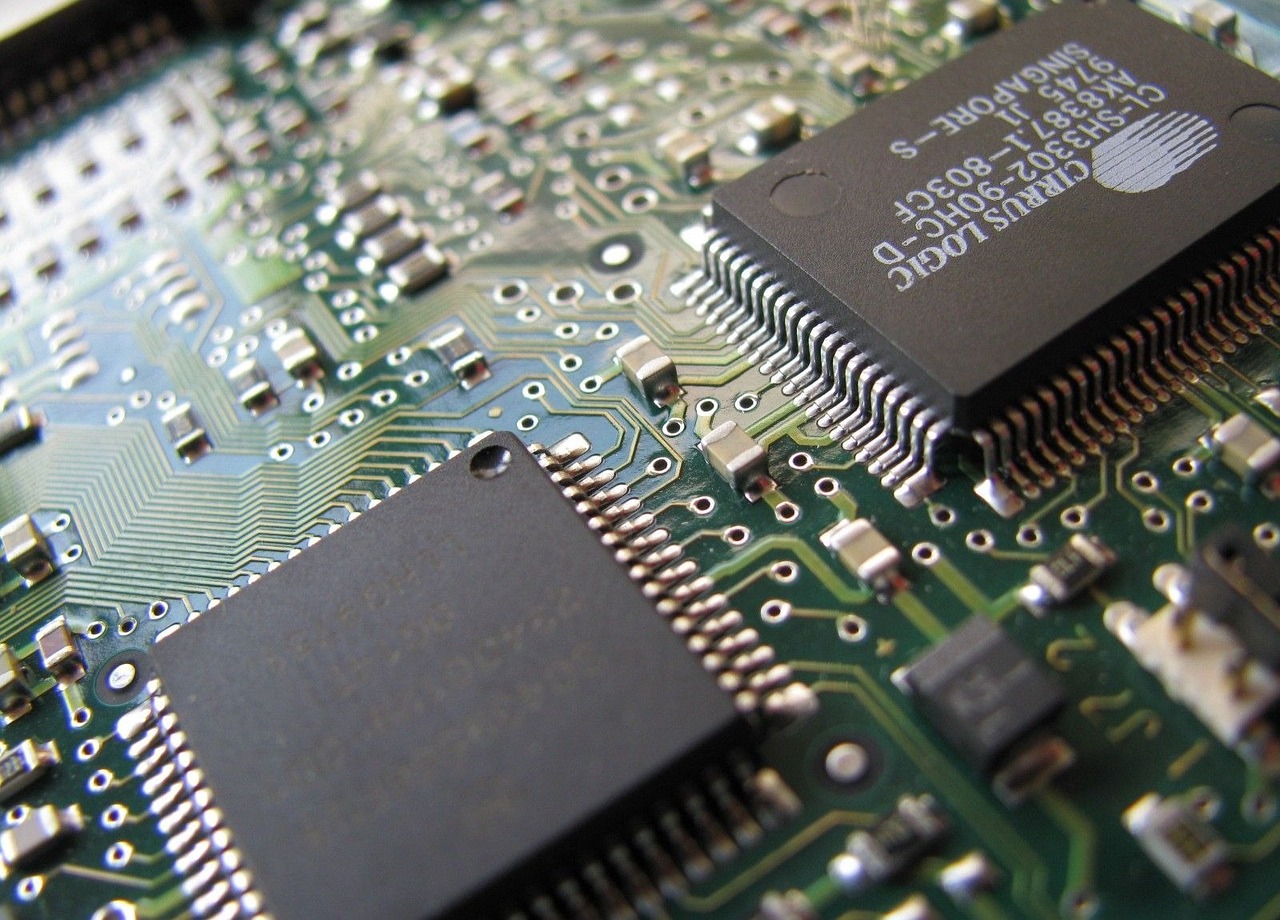
半導体製造装置市場は、その特性上、少数の企業による寡占化が進行しています。この市場構造は、TELのような既存の大手企業にとって有利に働いています。
寡占化が進む市場構造と高い参入障壁
半導体製造装置の開発と製造には、継続的な巨額の研究開発投資が不可欠であり、これが可能な企業は限られています。結果として、各工程で強みを持つ企業がさらにその地位を強化し、市場の寡占化が進んでいます。
新規参入は技術面でもコスト面でも極めて難しい状況であり、既存企業の優位性が増す構造となっています。この市場には、高い物理的な参入障壁が存在します。
半導体製造装置市場の寡占化は、単に技術力や資金力がある企業が強いというだけでなく、顧客である半導体メーカーが特定の装置メーカーに依存する「ロックイン効果」を生み出しています。
一度導入された装置は、その後のメンテナンスやアップグレード、プロセス最適化のために、同じメーカーからの継続的なサポートが不可欠となるため、新規メーカーへの切り替えは極めて高コストでリスクが高いとされます。この構造が、TELのような既存の大手企業の地位をさらに強固にしています。
主要競合他社との比較における東京エレクトロンの競争優位性
半導体製造装置市場には、ASML(オランダ)、Applied Materials(米国)、Lam Research(米国)といった強力な競合他社が存在します。TELはこれらのグローバルプレイヤーの中で、特定の分野で圧倒的な強みを発揮することで競争優位性を確立しています。
表2:主要半導体製造装置カテゴリーにおける東京エレクトロンの市場シェアと競合他社との比較
| カテゴリー | 主要競合他社(国) | 東京エレクトロンの市場シェア/順位 |
| 全体売上高ランキング | ASML (オランダ), Applied Materials (米国), Lam Research (米国) | 3位 |
| 露光装置 | ASML (オランダ), ニコン (日本), キヤノン (日本) | TELは当該分野で主要なシェアなし (ASMLが92.8%で圧倒的) |
| 塗布・現像装置 | SCREEN (日本) | 84.1% (1位) |
| 成膜装置 | Applied Materials (米国), Lam Research (米国), ASM (オランダ), KOKUSAI ELECTRIC (日本) | 14.0% (3位) |
| エッチング装置 | Lam Research (米国), Applied Materials (米国), 日立ハイテク (日本) | 25.3% (2位) |
この表から、TELが半導体製造装置市場全体でトップ3に入るだけでなく、特に塗布・現像装置という特定のキープロセスにおいて圧倒的な市場シェア(84.1%)を持つことが明らかです。
これは、TELが半導体製造の連続した4つのキープロセス全てに製品を持つ世界で唯一のメーカーであるという強みと相まって、競合他社にはない包括的なソリューション提供能力を顧客に提供していることを示しています。
ASMLが最先端露光装置で圧倒的な地位を築いているように、各社が特定の工程で強みを持つ中で、TELは複数の主要工程で上位を占めることで、総合的な製品ラインナップの強みを発揮し、戦略的なポジショニングを確立しています。
将来展望:持続的成長への戦略

半導体市場は、IoT、AI、5G通信、自動運転、バーチャルリアリティなどの新技術の普及により、今後も急成長が予想されています。
大規模な計算を必要とするこれらのアプリケーションがテクノロジードライバーとなり、半導体市場は2030年には1兆米ドル規模に達すると予測されています。TELは、このような市場の成長を支える半導体の技術革新に貢献するため、高付加価値の次世代装置の継続的な創出を目指しています。
そのための具体的な戦略として、TELは中期経営計画において、2025年3月期からの5年間で研究開発投資1.5兆円以上、設備投資7,000億円以上という大規模な投資を計画しています。これは、ナンバーワン・オンリーワンの強い次世代製品をタイムリーかつ継続的に創出するための「生命線」と位置付けられています。
また、事業拡大を見据え、今後5年間で1万人のエンジニア採用も計画しており、新卒採用枠500人に対し2万5000人以上の応募があるなど、人材獲得競争力も高く、成長のための基盤強化を進めています。
しかし、半導体産業は地政学的リスクにも晒されています。TELの株価が低迷する背景には、中国事業の割合が高いことへの懸念があると指摘されています。
AI開発に不可欠な半導体の需要拡大を受け、TSMCのような大手半導体メーカーがアメリカや日本での工場建設を加速させているのは、地政学的緊張の高まりが背景にあります。
米国のCHIPS法も国内製造強化を目的としており、半導体産業が国家安全保障と密接に結びつく中で、特定の地域への依存度が高いことは、今後の持続的成長における重要なリスク要因となります。
TELは技術的な優位性と明確な成長戦略を持つ一方で、政治的・外交的リスクへの対応能力が今後の経営においてより重要になることを示唆しています。
結論:日本の半導体産業における東京エレクトロンの意義
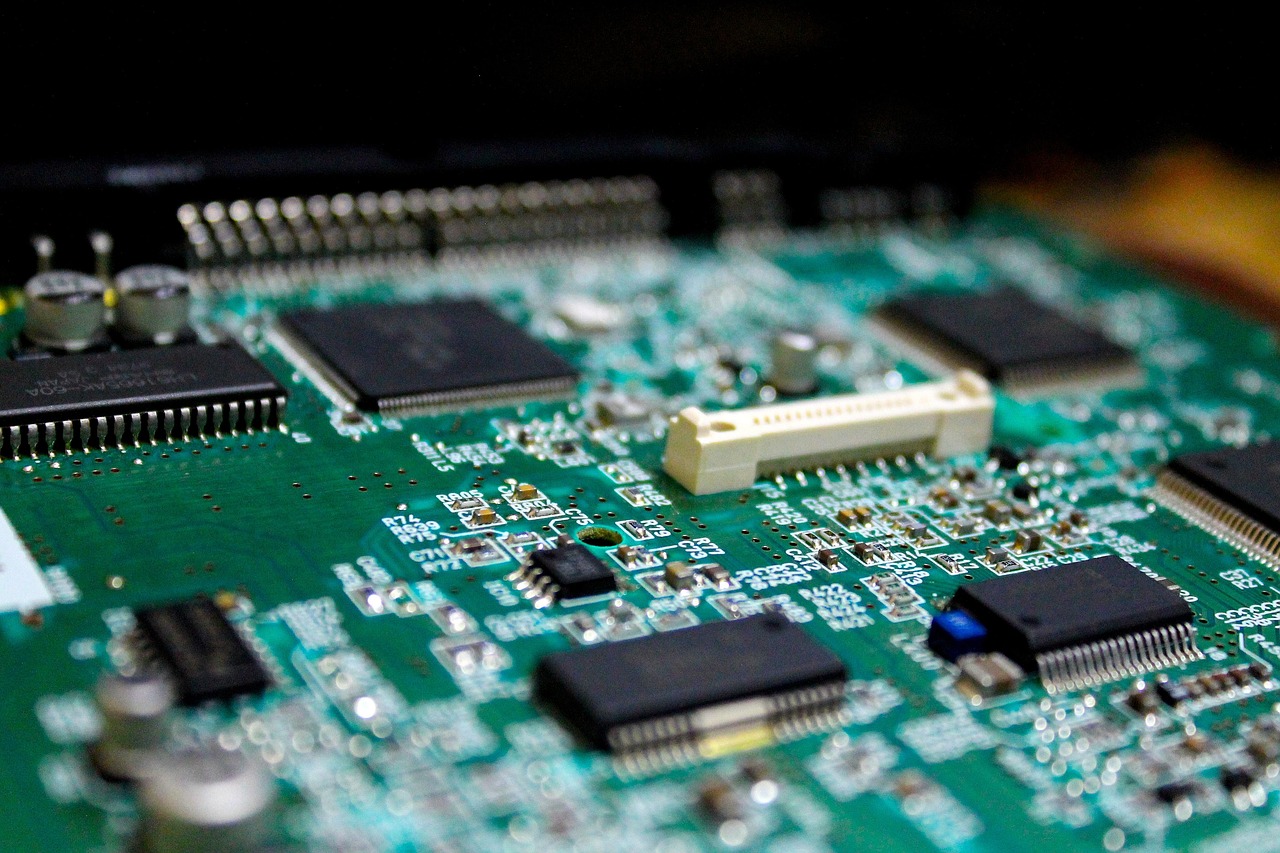
日本の半導体産業が全体としてアメリカや台湾に遅れを取っているという認識は、主に半導体チップの設計・製造(ファブレス・ファウンドリ)分野における過去の戦略的誤判断と外部環境の変化への適応遅延に起因します。しかし、この認識は半導体産業のサプライチェーン全体を包括的に捉えたものではありません。
東京エレクトロンの突出した存在は、まさにこの日本の半導体サプライチェーンにおける真の強みを体現しています。TELの成功は、以下の複合的な要因によって支えられています。
- 歴史的転換点における戦略的決断: 創業時の輸入商社から、日米半導体摩擦を契機に製造メーカーへと大胆に転換し、自社技術の内製化と製品ラインナップの拡充を進めました 9。
- 飽くなき技術革新と巨額のR&D投資: 半導体微細化の最前線を支える「ナンバーワン・オンリーワン」製品(EUV露光用塗布現像装置で100%シェアなど)を創出し、業界トップクラスの研究開発投資と特許戦略によって技術的優位性を確立しています 12。
- 顧客密着型開発と強固な信頼関係: 世界最大の装置出荷実績を背景に、顧客の歩留まり向上や稼働率最大化に貢献する高付加価値サービスを提供し、アフターマーケットでの安定的な収益を確保しています 12。これにより、顧客にとって代替不可能なパートナーとしての地位を確立し、強固なロックイン効果を生み出しています。
- 包括的な製品ラインナップとニッチ市場での圧倒的優位性: 半導体製造の主要4プロセス全てに製品を持つ世界で唯一のメーカーであり、特に塗布・現像装置で圧倒的なシェアを誇ることで、顧客に包括的なソリューションを提供し、競争優位性を確立しています 12。
- 寡占化された市場構造における優位性: 半導体製造装置市場の高い参入障壁と、継続的な巨額投資が必要な特性を背景に、既存の強固な地位を盤石にしています 15。
結論として、東京エレクトロンの成功は、日本の半導体産業が、チップそのものの製造競争では後塵を拝したものの、その製造を支える「縁の下の力持ち」としての技術力と市場支配力を維持していることを明確に示しています。
特に、半導体材料分野における日本の圧倒的な優位性(シリコンウェーハ、フォトレジスト、高純度フッ酸などで世界シェアの多くを占める)は、世界の半導体サプライチェーンにおける日本の不可欠な役割を裏付けています 7。
今後、AIやIoTの進化に伴い半導体需要が拡大する中で、日本は半導体製造装置と材料という強みを持つ分野で、引き続き世界の技術革新を支える戦略的な地位を確立していくことが期待されます。
国家レベルでの投資(兆円単位の国家プロジェクト)により、この強みをさらに強化し、製造業全体の地盤沈下を防ぐことが、日本の半導体産業の持続的な発展にとって極めて重要であると言えるでしょう 17。